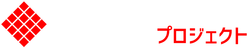|
AI、ボット、クラウドなど、テクノロジーの驚異的進化の真っただ中にあって、どうしても“新しいもの”にばかり目を奪われがちです。 コールセンターの管理者にとって、その優先順位が高いのは当然ですが、足元のオペレーションが脆弱なままでは迫りくる大きな変化の時代に勝利することはできません。 今こそ、旧態依然としたセンター運営から脱却し、「コールセンター・マネジメントの絶対基準(基本形)」にもとづく盤石な態勢を築いておくべきです。 そこで以下に、「間違いだらけのセンター運営チェックリスト――ビジネスプロセス編」を示します。 このリストは、「コールセンターの教科書プロジェクト」の武者昌彦さんの協力を得て、コールセンターのオペレーションの中核であるビジネスプロセスに関する、数社のセンター長による発言を集めたものです。 まさに“旧態依然”を象徴するようなセンター運営の“あるあるチェックリスト”と言い換えられる内容です。
いかがでしょうか。 もしひとつでも心当たりがあれば、今すぐにあなたのセンターの運営の見直しを始めてください。 いくつかの発言は、それ自体が問題とは言い切れないものもありますが、その背景や、発言にともなう行動も含めて考えていただくと良いでしょう。 それぞれの発言に関するソリューションや「基本形」については、『コールセンター・マネジメントの教科書』で確認いただくか、「コールセンターの業務設計講座~ビジネスプロセス・マネジメント編~」の受講をおすすめします。
0 コメント
日本企業は、技術系の分野においては世界をリードするプロセスやノウハウを持ちながら、一般事務系オフィスワークにおいてはからきし弱いと言われます。 個人の暗黙知に頼り、集団で助け合いながら仕事をするという日本流のスタイルが、個人の役割や責任をあいまいにし、それによってムリ・ムラ・ムダや無責任体質を引き起こします。 その結果、時間当たりの労働生産性が、主要先進7カ国中37年連続で最下位(日本生産性本部)に甘んじるという不名誉な状況を招いているのです。 この日本流のスタイルでコールセンターのオペレーションを運営しようとするから、上手くいかないのです。 コールセンターのオペレーションは、顧客とエージェントの1対1のコミュニケーションの集合体です。 つまり、仕事の最小単位である1つひとつのコンタクトは、1人ひとりのエージェントが他から明確に独立して仕事をしているため、そこに“集団”が介入する余地はありません。 また、個人の暗黙知に頼ることで、コールセンターの生命線である“一貫性”が損なわれ、次のような事態を招きます。
このような状態から抜け出すために真っ先におこなうべきなのが、仕事の可視化と標準化です。 可視化・標準化するのは、チームの仕事だけでなく、個人(注)の仕事についても必要です。 この、個人の仕事の役割や責任を明確にするのが「ジョブ・ディスクリプション」です。 ジョブ・ディスクリプションには、企業やセンターのミッションや目的を達成するために、各ポジションが果たすべき役割や責任が定義されています。 多くのスタッフが集う一方、1つひとつのコンタクトが独立しているコールセンターだからこそ、全員の意識と行動に一貫性を確保するために、ジョブ・ディスクリプションは必須のツールなのです。 さらに、ジョブ・ディスクリプションが存在することで、自分が担うポジションのあるべき姿と自分の現状とのギャップを具体的に知ることができ、それを埋めるためにスキルや能力の強化を図るなど、自己啓発のためのツールとしても機能します。 ジョブ・ディスクリプションは、コールセンターにとって“Nice-to-have”でなく“Must have”のツールなのです。 ※ジョブ・ディスクリプションについては、『コールセンター・マネジメントの教科書』第2章(P.74~76)で、作成の仕方について詳しく説明しています。また、代表的な7つのポジションのジョブ・ディスクリプションのサンプルを掲載(P.556~564)しています。
「Nice-to-Have」は、「あれば良いもの」、言い換えれば「なくても構わないもの」のことで、「物理的なもの」(念のために保存している資料など)と「行為」(万が一の場合の2重、3重のチェックなど)のふたつの要素があります。 コールセンターに限らず、一般的なビジネス用語としてご存知の方も多いのではないでしょうか。 「Avoidable Input」と「Nice-to-Have」が、コールセンターの改善によく効くというのは、“モグラたたき”や“なくても構わない過剰な作業”が、オペレーションの現場に多く見られる“悪いクセ”であるためです。 「細部にこだわる」というコールセンターの特性が行き過ぎることによって、この2つが現れやすくなるのです。 したがって、このふたつの視点を持って現場のオペレーションに目を凝らすと、いくつもの“改善ネタ”を容易に見つけることができます。 両者には“連係プレイ”も見られます。 例えば、年に一度のエラーのために毎日コールの全件をチェックするという行き過ぎた作業(Nice-to-Have)は、エラーの発生を前提としています。この行き過ぎた作業をなくすためには、そもそもエラーが発生しないよう、エラーの元を断つ(Avoidable Input)方が高い効果を得られます。 既存の業務を点検する時にも、新しい仕事を始める時にも、常に「Avoidable Input」と「Nice-to-Have」の視点で見る“クセ”をつけることで、無意識のうちに「継続的な改善」を実践できるのです。
2018年5月30日、『コールセンター・マネジメントの教科書』を発刊しました。
624ページにおよぶこの本に一貫して書かれているのは「基本」です。 私たちは、「基本」という言葉を日常生活のあらゆる場面でごく普通に使いますが、そこには大まかに2つの意味合いがあるように思います。 ひとつは「最も重要なもの」、もうひとつは「初歩的なもの」というニュアンスです。 類語辞典を検索してみると、「起点」「本質」「核心」「真髄」「最重要」といった前者に近い言葉と、「入門」「初級」「初歩」「イロハのイ」といった後者に近い言葉が混在しています。 コールセンターのマネジメントの場面においてはどうでしょう。 筆者の経験からは、圧倒的に後者の意味合いで使われることが多いように思います。 それが最も如実に表れているのが、トレーニング(教育・研修)の分野でしょう。 ほとんどの場合、「基本」と名がつくトレーニングは、新人など経験の浅いスタッフを対象としています。 コールセンター業務の経験がない新任の管理者が受講することはあっても、センター長やマネージャーと呼ばれるポジションの人たちが、「基本」のトレーニングを受けることは極めてまれです。 では、そんなセンター長やマネジャーの人たちには、「基本」がしっかりと身に付いているのでしょうか。 以下は、いずれもコールセンター・マネジメントの「キホンのキ」を理解していない事例ばかりです。 これをお読みのセンター管理者の皆さん、ダイジョーブですよね?
② 500コール × 90%=450コール・・・・・・応答すべきコール数 ③ (450コール × 300秒) ÷3,600秒=37人・・・・・・フル稼働の場合のエージェント数 ④ 37 ÷ 85%=43人・・・・・・稼働率を考慮に入れたエージェント数
いかがでしょう。「基本」を理解している人なら、これらすべてがナンセンスであることをおわかりのはずです。 もしこれらに違和感を感じなければ、あなたのセンターは、顧客、エージェント、企業のいずれにとっても、ハッピーな存在ではないかもしれません。 「基本」の理解や徹底が十分でないことは、正常なセンター運営の妨げとなるからです。 センター・マネジメントにおける「基本」は、決して「初歩的なもの」として軽んずべきものではなく、「最も重要なもの」であることに気付いてください。 確かに時代は大きく変化しています。しかし、時代がどれだけ大きく変化しようと、環境がどれだけ異なろうと、マネジメントの「基本」は普遍であり不変です。 「新しいやり方」は「基本」の上に追加されていくものであることを忘れないでください。 そんな「基本」の重要性について、来たる7月11日、国内屈指のセンター長経験者4名が語ります。 ご興味のあるかたはこちらへ。 熊澤 伸宏(文/Vol. 1) |
|
サイトポリシー | プライバシーポリシー | 特定商取引に基づく表記 | Staff Only
Copyright © 2018 - 2022 コールセンターの教科書プロジェクト All Rights Reserved |
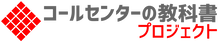




 RSSフィード
RSSフィード